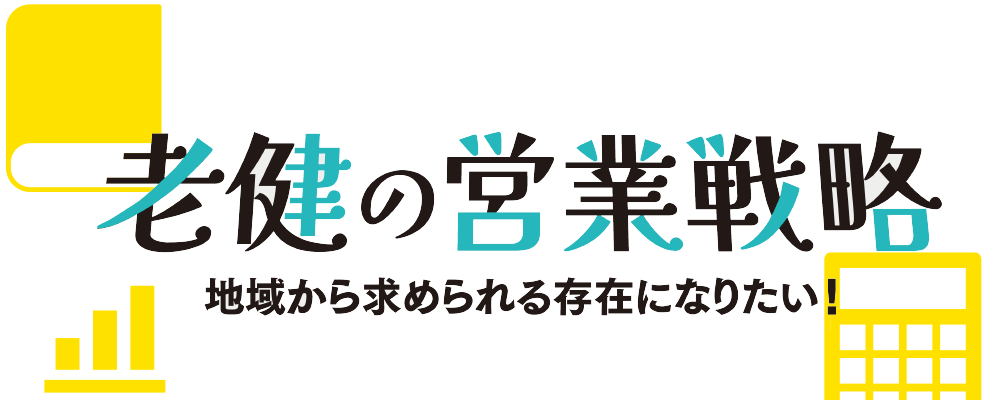
「利用者さんを集めるのが難しくなった」「見込みの利用者さんが見つからない」――。そんな声が巷でささやかれるようになった昨今ですが、老健の役割はまだまだあるはず。 地域が抱く老健のイメージに真摯に向き合い、既存のアプローチにとらわれない営業戦略を事例から考えます。
老健に期待しているのは、やはりリハビリです。しかしながら地域にはリハビリ施設が溢れており、特に昨今、通所リハビリにおいては特化型のデイサービスの勢いに押されている印象があります。リハビリ内容や料金もそうですが、診療情報提供書の作成やリハビリ会議の実施といった利用に際してやるべき事項が多いことも一因になっているのではないでしょうか。ただしそれは制度上必要なことですし、質の高いリハビリの提供には不可欠ではあるため、労力に見合う成果が出ることを期待したいです。
また地域連携においては自戒を込めていうと、いかに利用者さんの望みに応え、迅速な対応ができるかに尽きます。老健ほどの大きなキャパシティですから、判定会議に時間を要したり、体験利用や送迎時のフォローが手薄になるといった場面に出くわすこともあります。大変さは重々承知しているため、そこでの中間報告やちょっとした一言があると信頼感が生まれ、利用者さんの安心につながるのだと思います。
在宅復帰・支援施設としての老健の役割は、地域に浸透しています。ケアマネジメントの視点からも地域にもっと目を向けて、ともに高齢者の生活を支えていける存在になりたいです。
老健は、介護報酬改定の度にさまざまな機能が期待されている分、その特徴が年々わかりにくくなっているように感じています。当院が位置する後志管内においては、比較的柔軟に対応していただけている一方、褥瘡など医療依存度の高い患者さんの受け入れは断られることも多くあります。そのあたり、各施設の受け入れ条件や強みなどを積極的に発信していただけると、もっと円滑に連携できると思っています。
時折、老健からパンフレットや広報誌などを送付いただくこともあり、そこで利用者さんの様子や専門職の思いなどを知ることもあります。今後は、実際に連携するうえで活用できる情報提供も期待したいですし、私たち医療ソーシャルワーカーも積極的にキャッチしにいかなければならないと感じています。当協会では、医療と介護の連携に資する研修会なども多く開催しています。顔の見える関係を構築するためにも、もっと地域に出てきてほしいと願っています。
包括に勤務して半年間で、老健入所の支援ケースはまだ経験できていません。一方で関わりが多いのが虐待対応です。早期発見や介護者支援、レスパイトなど、包括だけでは担えるものでは決してありません。地域包括ケアシステムの中核を担う施設である老健とも、今後も連携させていただきたいと考えています。
医療法人北翔会 介護老人保健施設まいあの里(札幌市)
入所 80人/通所 77人/超強化型・単独型
【営業先】急性期病院、ときどき居宅介護支援事業所
【営業エリア】札幌、千歳、恵庭、苫小牧など。電話は道内全域
【入所ルート】病院50%、居宅介護支援事業所50%
【社会資源の状況】区内に老健が2つあるが、いずれも同施設よりも歴史が古く、 地域からの認知度が高い。このほかリハビリ施設も数多い。
営業活動は、自施設の利用者獲得のためだけではあらず。出来る限り地域の情報を集めることで、自施設が満床の場合は他施設への紹介ができるようにしている。同施設は、病院や居宅介護支援事業所を併設しないことから見込みの利用者が限られており、せっかく問い合わせがあっても紹介できるルートが少ない。そこで他施設を紹介することで、利用者も困らず、紹介先との持ちつ持たれつの協力体制も生まれやすい。いつか、利用に結び付くことを期待する考えからだという。ときには、施設紹介会社などとも情報交換を行い、地域の資源を把握しておく。
施設の方針として、基本的に薬価は5万円まで受け入れ可能としている。薬が必要だから服用しているのであって、上限を超えたから入所を断るというのは、利用者のニーズに応えていないのも同義との考えから。経営上からも、目先の収支にこだわるよりも全体最適の視点を重視している。
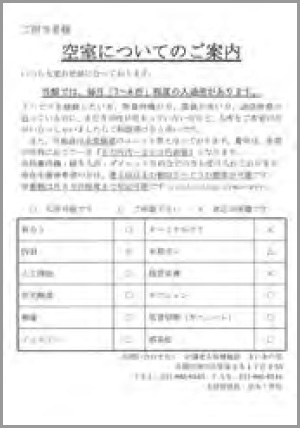
コロナ禍で通所利用者が激減したことをきっかけに、通所内容を再構築。「夢をかなえる通所リハビリ」をコンセプトに、利用者さんのやりたいことを第一に考え、プログラムを組み立てる内容へと刷新を図った。その結果、利用者が2.5倍に膨れ上がり、定員数も50人から77人へと拡充。地域住民、関係各所において同施設の認知度が上がっている。
特別養護老人ホームに営業するも、ほぼ反応がなかった。
入所相談は、基本的に断らないスタンスです。薬価もそうですが、水虫で毎日の足浴が欠かせないなどケア面で多少負担がかかるとしても、現場と調整して受け入れできるよう整えるのが私たちの努め。そのためにも地域の情報を集めることは大事ですし、地域を知ることで当施設のあり方が見えてくると思います。このような積み重ねで、少しずつ地域の老健になれてきているように感じています。
「面白いと思ったことはやってみる」が当施設のテーマ。コロナ前には、町内会で毎週開催していたカラオケ大会に足しげく通って交流を深めていました。コロナで追い込まれたときも立ち止まらず、現場職員で意見交換を行って通所リハビリの刷新やYoutube配信など新しいことにチャレンジできたおかげで、過去最高の収益を確保できています。施設が地域から選ばれる時代となり、厳しい反面、これが本来のあり方だとも思っています。

医療法人社団刀圭会 介護老人保健施設 アメニティ帯広(帯広市)
入所 100人/通所 39人/超強化型・併設型
【営業先】病院(回復期・地域包括ケア病棟)、有料老人ホーム、サ高住
【営業エリア】帯広市内、近郊
【入所ルート】病院70%、在宅30%(自宅、有料老人ホーム、サ高住)
【社会資源の状況】市内には、老健はじめグループホームや有料老人ホームなど多数点在する激戦区
老健から見ると有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅といえば、退所先のイメージが大きい。同施設も同様だったが、あるとき有料老人ホームやサ高住に退所した利用者さんが、数カ月後に病院から再入所するケースが数件発生。食事摂取量の減少やADLの極端な低下などが入院理由になっていたため、老健としての退所のあり方を見直す必要性を認識した。そこで、当該の有料老人ホームと話し合ったところ、特に特養待機者においてはリハビリやADLを維持するための老健入所が効果的との結論にいたり、逆紹介の仕組みを構築しつつある。
十勝管内にある老健の支援相談員のネットワークでは、毎月2回、居宅支援事業所や病院など約200施設に対し、空床状況を知らせるFAX営業を行っている。老健ならではのネットワークを活かした営業活動の好例。

ショートステイは1床のみだが、平均稼働率は3.0以上を維持。入所への足掛かりにもなっており、有効活用している。特に居宅サービスを利用する人にとっては、お試しの場としても役立っている。
回復期病棟や地域包括ケア病棟を有する病院に営業するも、なかなか紹介が増えない。十勝管内全域まわっていたこともあったが、労力に見合う成果が出なかった…。
ライフシップケア帯広株式会社ライフデザイン事業部部長 山本正人さん
コロナが収束したころから特養に空きがではじめ、退去者が続出したと思えば、時期によっては入居相談が立て続けにきて満室になるなど、予測がつかないことが増えました。そんなときにアメニティ帯広さんとの連携の話が浮上。当施設としては、満室時に待機いただく間、アメニティ帯広さんを利用いただければ適切なリハビリやケアが受けられますし、退所後の当施設への入居予測も立って空室対策にもなります。もちろんご本人や家族にとっても、リハビリによってADLの維持・向上が期待できる利点があります。 また、原則、入所期間に限りがある老健は次の行き先に不安を覚えるご家族も多いと思われますが、当施設のように一つでも多くの連携先があるのは、安心感につながるはずです。課題はまだありますが、老健と有料老人ホーム間でより円滑に連携できるあり方を考えたいです。
これまで有料老人ホームとしても、利用者さんが体調不良を起こしたときなどは病院に入院することがほとんどだったようで、老健は選択肢には含まれていませんでした。新たなニーズの発見ができたので、紹介を増やしていけるように取り組みたいです。同時に法人内の関連施設とも情報共有を深め、相談しやすい関係構築を目指します。

今回の有料老人ホームさんとの連携については、担当が代わってもきちんと継続していけるよう、互いの施設を行き来するメリットやルールなどを明記した協定書を作ろうと考えています。リハビリが必要になったらまた戻ってこれるという一文があると、施設はもちろん利用者さんやご家族にとっても安心材料の一つになるかもしれません。この仕組みが軌道に乗ったあかつきには、他の老健にもすすめたいと思います。もっと多くの利用者さんのニーズに応えられるよう、地域で協力していきたいですね。

医療法人歓生会 介護老人保健施設フェニックス(旭川) 支援相談員 宮崎拓也さん
超強化型を維持すべく、当施設が参画している地域の見守り事業で、地区社協や成年後見支援センターに向けて老健の活用をPRしてきました。何度か合同で勉強会も開催して地域での認知度は上がっているものの期待していたほどの紹介には結びつかなかったほか、紹介があっても医療依存度の高い利用者が増えて現場に負担がかかり、在宅復帰が難しい状況にありました。そこで着目したのが、 2024年度の診療報酬で新設された「地域包括医療病棟」を有する病院へのアプローチです。同病棟は、リハビリによって早期に在宅復帰を目指す病棟のため、老健も退院先になり得ると考えました。そもそも当該病院における運営がまだ軌道に乗っていないことから実績はないのですが、3カ月に1度の定期的な打ち合わせを行うこととなりました。さまざまな可能性を考え、働きかけていきたいです。
おなじみ北海道医療ソーシャルワーカー協会が主催する「ソーシャルワークセミナー」が今年も開催されます。今回は、支援相談員のみならず多職種が参加することで、より議論が深まる内容にしています。皆さまのご参加をお待ちしています!
日時/2025年2月15日(土) 13:30~17:00
場所/オンライン開催(参加費無料)
申し込み〆切/2月5日
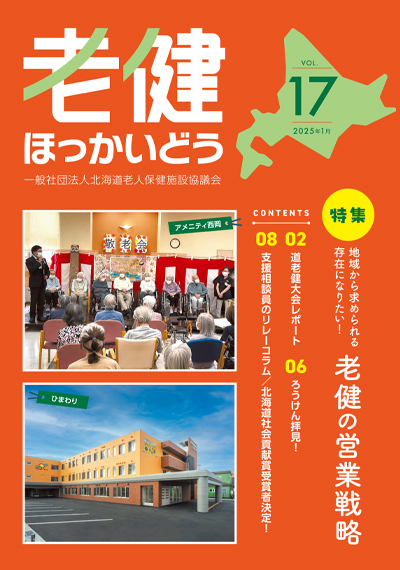

老健ほっかいどう vol.17/3P
令和7年1月発行